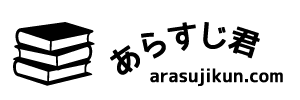【昔話】石仏の怪【あらすじ・ネタバレ】
むかしむかしあるところに、百姓のおじいさん一家が住んでいました。
ある日、おじいさんの孫が子馬と一緒に村の石橋から落っこちて大ケガをしました。
2日後の朝、近くに住む若者が馬を引いてこの石橋を渡ろうとすると、馬が橋の真ん中で動けなくなりました。
その翌日には、また別の若者も石橋に足がくっついて動けなくなり、これは幽霊橋だという悪い噂が村中に流れました。
村人たちは、この石橋を調べてみることにしました。
隣村からお坊さんを呼んでお経をあげてもらいながら、村人たちが橋の石板をひっくり返してると、石板から「角田掃部助藤原久吉」という殿さまの名前が刻まれた仏が出てきました。
大昔、この殿さまは、村に悪い病気におかされてしまったときに、村人たちのために奔走し、その結果自分が倒れてしまったのでした。
それを哀しんだ村人たちがこの仏を作ったのでした。
そんな大切な仏が、なぜこのように粗末に扱われていたのかは分かりませんが、きっと殿さまが訴えていたのかもしれないと村人たちは思いました。
そこで村人たちは仏を橋の脇に安置し、石板を新しいものと交換しました。
今ではこの仏の前にはお線香が絶えず、大切にされています。